「フリーランスエンジニアと法人化の違いってなに?」「フリーランスから法人化すると、どんなメリットやデメリットがあるの?」このような疑問や悩みをお持ちではないでしょうか?
この記事では、フリーランスと法人化の違いや、法人化の特徴について紹介しています。
最後まで読むことで、法人化の特徴やメリット、注意すべき点について理解できるでしょう。
また、記事の後半では法人化の手続きや、登記する際の注意点について解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
法人化するのにおすすめなフリーランスエージェントなら「レバテックフリーランス」がおすすめです。
レバテックフリーランスは、フリーランスとフリーランスを採用したい企業の仲介をおこなっている人材サービスです。
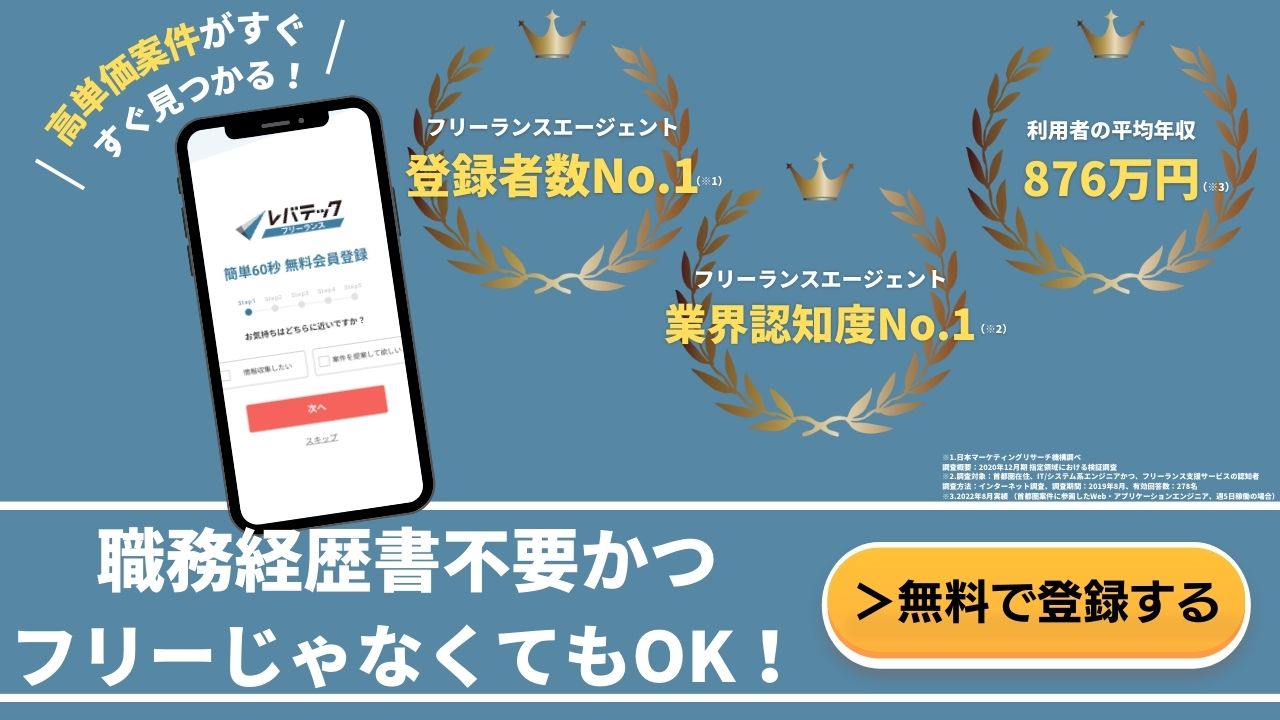
「レバテックフリーランス」は、登録者数No.1のフリーランスエージェントで、その登録者の平均年収が862万円と脅威の数字を誇っています。
登録者が多いのにもかかわらず、平均年収が高いということはそれだけ『1つの案件に対する単価が高い』ということです。
 今の単価よりも少しでも高くしたい方は登録して案件を紹介してもらいましょう。登録はもちろん無料ですし、案件を見るだけの登録でもOKです!
今の単価よりも少しでも高くしたい方は登録して案件を紹介してもらいましょう。登録はもちろん無料ですし、案件を見るだけの登録でもOKです!
- その他のエージェントの比較も見る
フリーランスエンジニアと法人の違いは?法人化について解説

法人化の詳細と、フリーランスエンジニアと法人の違いについて解説します。
フリーランスエンジニアの法人化とは?
法人化とは、フリーランス(個人事業主)を廃業し、会社を設立するための手続きをおこなって法人へ移行することを指します。
一言で法人化と言っても、会社形態には以下の2つがあり、それぞれ特徴が異なります。
- 株式会社/出資者と経営者が異なる
- 合同会社/出資者と経営者が同じ
株式会社と合同会社は同じ「普通法人」となるため、法人税などは同じです。
ただ、株式会社は会社設立のコストがかかるため、できるだけ安く法人化したい場合は、合同会社がよいでしょう。
※株式会社は、定款の認証が必要なことと、登録免許税が合同会社よりも高い特徴があります。
フリーランスエンジニアと法人|手続きや費用の違い
フリーランスエンジニアと法人では、法的な手続きや事業運営にかかる費用に以下の違いが見られます。
【フリーランスエンジニアの場合】
- 事業をはじめる際に法的な手続きや申請が必要ない
- 事業運営にかかる維持費が法人に比べて少額
- 白色申告では複式簿記が可能
- 利益が大きいほど税率が高くなる(最高税率45%)
【法人の場合】
- 法人化するにあたって煩雑な手続きや申請が必要になる
- 開業や経営に多額のコストがかかる
- 社会保険料の支払いが重くなる
- 利益が大きいほど税率が低くなる(資産1億円未満の場合)
フリーランスエンジニアと法人|税金と経費の範囲の違い
フリーランスと法人化には、税金と経費の範囲に大きな違いがあります。
フリーランスは、経費計上の割合が少なく、利益が大きくなるほど税率が上がる累進課税が適用されます。※最高税率は45%
一方、法人は課税所得800万円以下が19%、800万円超が23.20%と一定所得以上になると個人事業主より税率が低くなるのです。
※資産1億円未満の中小企業の場合
※課税所得が900万円以上の税率は、個人事業主が33%、法人が23.20%
また、資産1億円未満の法人の場合、年間800万円まで経費計上が可能です。
フリーランスエンジニアが法人化(法人化成り)をする6つのメリット

フリーランスエンジニアから法人化(法人成り)をするメリットについて、6つ解説します。
役員報酬や退職金の損金計上が可能になる
フリーランスから法人化することで、役員報酬や退職金の損金計上が可能になります。
損金計上(損金算入)とは、法人が収入を得るためにかかった費用を、損金として計上することです。
損金として認められるものは、法人事業税や所得税など各種税金がありますが、役員報酬や退職金も該当します。
消費税が2年間免除されることがある
以下の条件を満たして免税事業者になると、消費税が最大2年間免除になります。
- 資本金が1,000万円未満であること
- 特定期間の課税が1,000万円以下であること
- 特定期間の給与支払額が総額1,000万円以下であること
- 設立1期目7ヶ月以下であること
また、フリーランスと法人の特定期間は異なるため注意しましょう。
【特定期間】
- フリーランス(個人事業主)/1月1日~6月30日
- 法人/法人が判定する事業年度の前事業年度開始日から6ヶ月
社会的信用が高くなる
フリーランスエンジニアから法人化すると、以下の3つの理由から社会的信用が高まります。
- 第三者が謄本にて企業情報を確認できるようになるため
- 自分自身が保証人になることができるため
- 開業や経営が可能な多額の費用を持ち合わせているため
社会保険の加入が可能になる
法人化することで、各種社会保険に加入することができます。
フリーランス(個人事業主)は、国民年金と国民健康保険のみの加入が一般的です。
しかし、法人化することで、健康保険や介護保険、国民年金のほかに「厚生年金」に加入することができ、加入できる年金制度が増えることで、将来受け取れる年金額を増やすことができます。
また、病気やケガなど、入院などで一時的に働けなくなった場合は「傷病手当」の受給が可能です。
決算期を自由に選択できる
決算期が自由に選べることも、法人化のメリットです。
フリーランス(個人事業主)の決算期は、毎年12月と定められており、変更ができません。
※毎年1月1日~12月31日の収支から利益を計算します。
一方、法人化して決算期が自由に決められると、自社の都合で決算期を調節し、事業運営がしやすくなります。
たとえば、繁忙期を避けて閑散期に決算期を設定し、確定申告を済ませることで、仕事の負担を軽減できるのです。
個人事業主から法人化すると助成金が得られることがある
会社設立時に、以下の助成金や補助金の申請ができる場合があります。
- 創業支援等事業者補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- 地域中小企業応援ファンド
- キャリアアップ助成金 など
会社の資金繰りを良くするためにも、申請できる助成金や補助金を調査し、効率よく活用しましょう。
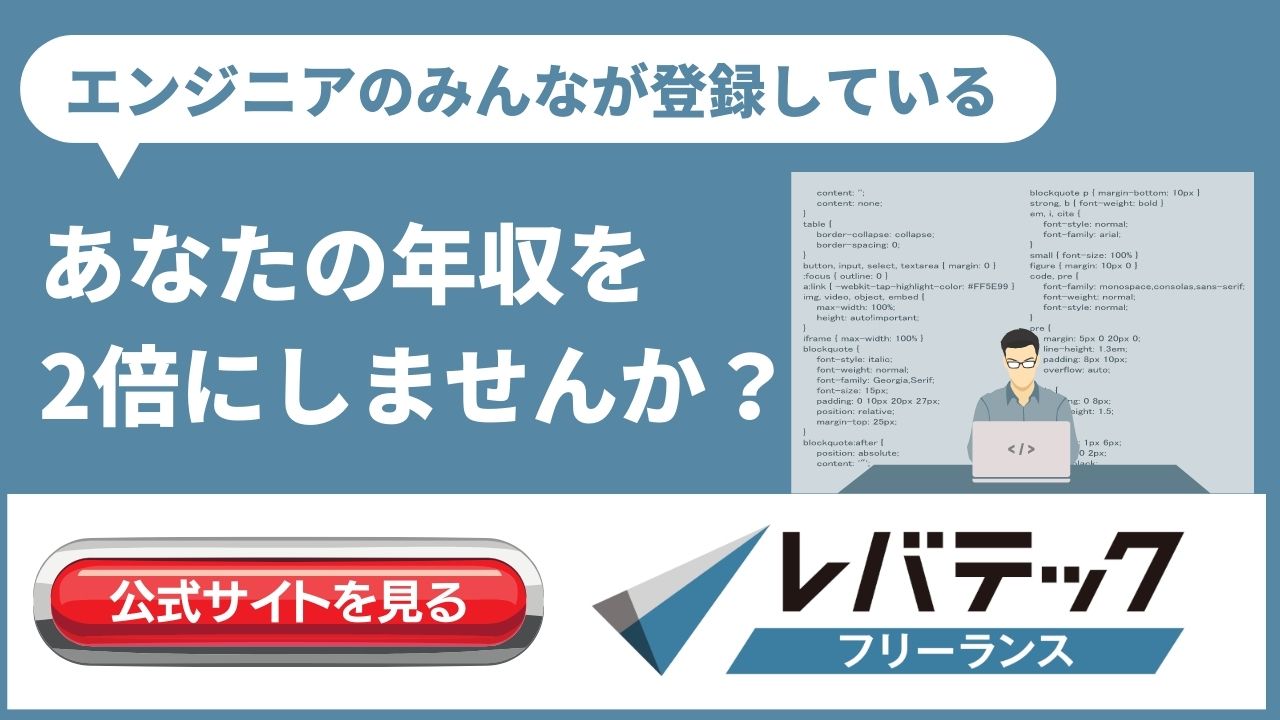
フリーランスエンジニアから法人化(法人化成り)にする4つのデメリット

フリーランスエンジニアから法人化(法人成り)することでデメリットになる4つを解説します。
法人化するのに費用がかかる
フリーランスの場合、事業運営に多額の費用はかかりません。
一方、法人化には会社形態によって異なる開業費が必要になります。
開業費の目安は、株式会社が約25万円〜、合同会社が約10万円〜です。
赤字でも税金が課せられる
法人化すると、たとえ赤字でも納税しなくてはなりません。
法人の場合は、法人住民税の均等割りである7万円を毎年納める必要があります。
会社を経営しはじめたら「毎年最低7万円は課税される」ことを忘れないようにしましょう。
社会保険料の支払い負担が大きくなる
法人化すると、社員が社長ひとりでも社会保険に加入する必要があるため、保険料の支払い負担が大きくなります。
社会保険料は保険の種類によって、負担割合が異なります。
※各種保険料は会社と社員の双方が折半で負担
- 健康保険/標準報酬月額×健康保険料率(都道府県により異なる)
- 厚生年金/標準報酬月額×18.30%(厚生年金保険料率)
- 介護保険/標準報酬月額×1.80%(介護保険料率)
また、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料は賞与からも控除されるため、注意が必要です。
役員報酬の変更が困難になる
法人化して一度役員報酬を決めてしまうと、変更することが難しくなります。
役員報酬は、事業開始から3ヶ月以内であれば一度だけ変更が可能です。
4ヶ月目以降に役員報酬を変更(増額)すると、増額した範囲は損金算入ができず、課税対象になります。
役員報酬は売上に応じて自在に変更できないため、金額を決める際は十分注意しましょう。
フリーランスエンジニアが法人化を検討する2つの理由
フリーランスエンジニアが法人化を検討する2つの理由について解説します。
フリーランスエンジニアは計上できる経費が少ないから
フリーランスエンジニアは法人と違い、経費計上できる割合が少ないのが現実です。
フリーランスと法人では、経費計上できる割合や税率が異なり、一定の所得を超えた段階で法人化を検討するのが得策です。
経費計上や税率に関する詳細事項は「税金と経費の違い」をご覧ください。
マイクロ法人だと社会保険料や税金を節約できるから
社会保険料や税金の節約目的で、マイクロ法人を検討するケースも多々あります。
マイクロ法人とは、社員が社長本人のみ、または身内のみで運営されている会社のことです。
マイクロ法人は、以下のメリットがあります。
- 所得税や社会保険料の負担を軽くできる
- 消費税が免除される「免税事業者」になれる
フリーランスエンジニアが法人化しない方がよかったと後悔したこと

フリーランスエンジニアが法人化して後悔したこと(失敗談)について解説します。
社会保険料の支払いに苦労した
フリーランスから法人に移行して、社会保険料の支払いに苦労した失敗談は多々聞かれます。
法人化することで、社会保険料が重くのしかかり、経営が厳しくなることは珍しくありません。
多くの案件を受注しても売上が伸び悩んでいる場合は、無理に法人化せず個人事業主を継続するのがよいでしょう。
経費がかかりすぎて節税効果を感じられない
法人化して想像以上にコストがかかり、節税の恩恵が受けられなかったという声も聞かれます。
法人は利益が高いほど税率が低くなり、節税効果を発揮します。
税理士の雇い入れなど、多額の経費がかかると予測される場合は、法人化しないのが賢明です。
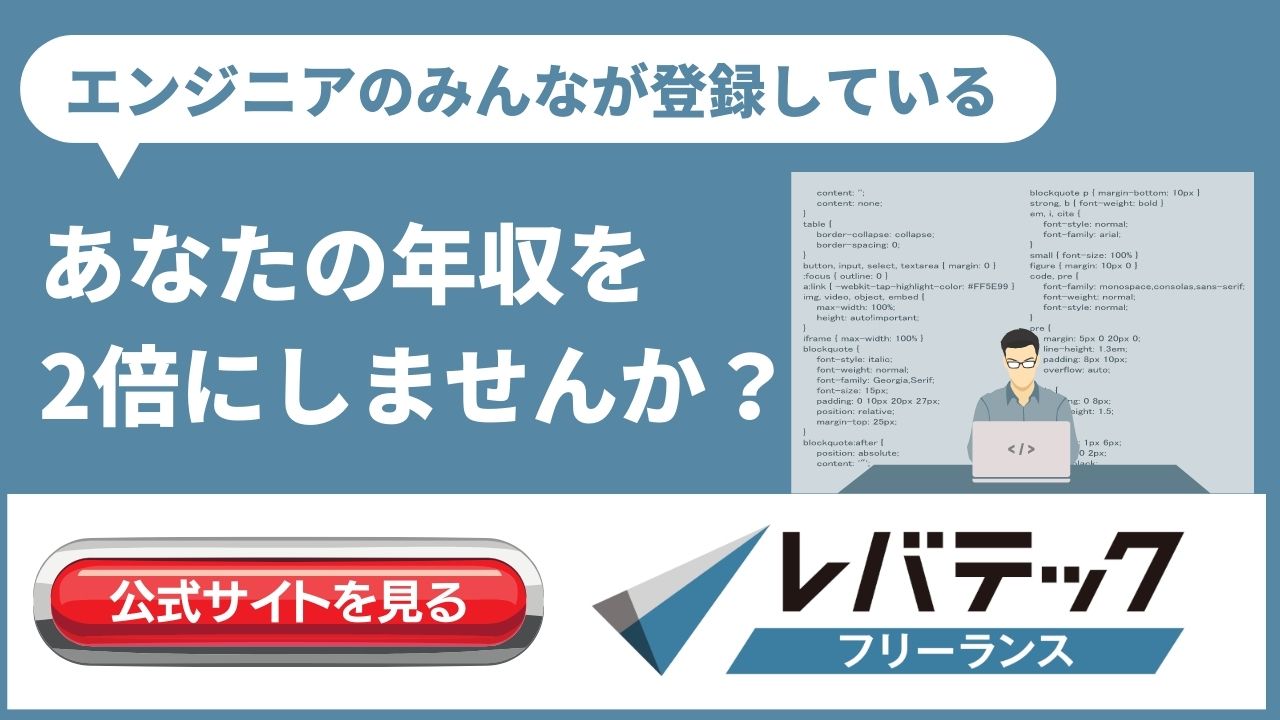
フリーランスエンジニアが法人化する最適なタイミングはいつ?

フリーランスエンジニアが法人化するタイミングについて紹介します。
年収が1,000万円を超えたとき
年収(売上)が1,000万円を超えたタイミングで法人化するのがベストです。
なぜなら、年間の売上が1,000万円を超えると消費税の課税対象となり、節税対策が必要になるからです。
法人化して一定の条件を満たすことにより、消費税が最大2年間免除され、節税ができます。
なお、消費税免除の詳細は「消費税が2年間免除されることがある」をご参照ください。
サラリーマンの場合は毎月の副収入が50万円を超えたとき
会社員のかたわら副業をおこなっている場合は、毎月の副収入が50万円を超えたときに法人化を検討してみましょう。
理由は以下のとおりです。
- 所得が350万円~400万円あたりで確定申告した場合、税率が法人を超えるため
- 会社設立のための事務手続きや事業運営に多額の費用がかかるため
サラリーマンから法人に移行するタイミングは、さまざまな考え方があるため、上述の売上額は目安として捉えてください。
フリーランスが法人化する5つの手続き
フリーランスが法人化する5つの手続きについて解説します。
設立登記を申請する
フリーランスから法人へ移行する際は、会社名や所在地、資本金、役員などを決め、設立登記を申請する必要があります。
設立登記の申請には、以下のものが必要です。
- 申請書
- 会社の基本情報をまとめた定款
- 印鑑証明
- 資本金振込の証明が可能な通帳のコピー
法人口座を開設する
法人化するにあたり、法人口座を開設するケースもあります。
法人口座の開設は任意のため、個人名義の口座を事業取引きに使用しても問題ありません。
法人口座に適した金融機関は以下の4つです。
- 都市銀行
- 地方銀行
- ネット銀行
- 信用金庫
法人口座の手続きに必要な書類は金融機関によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
役員報酬を設定する
事業開始から3ヶ月以内に役員報酬を決める必要があります。
役員報酬は、事業年度途中で変更することができないため、慎重に決めていきましょう。
役員報酬の詳細は「役員報酬の変更が困難になる」をご参照ください。
諸官庁へ届け出をする
設立登記を申請したら、会社所在地管轄の諸官庁へ以下の書類を提出しましょう。
- 法人設立届出書
- 青色申告承認申請書
- 給与支払事務所などの開設届出書
- 源泉所得税の納税特例承認に関する申請書
また、会社設立後に個人事業主の廃業手続きも忘れずにおこなってください。
健康保険や年金の加入手続きをする
社会保険(健康保険・厚生年金・介護保険)の加入は、年金事務所で行います。
社会保険は、社員全員の加入が義務づけられています。
たとえ社員が社長ひとりでも、役員報酬を受け取る場合は加入が必須です。
なお、社会保険の加入には以下の書類が必要になります。
- 健康保険 厚生年金保険新規適用届
- 健康保険 厚生年金保険被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者(異動)届
フリーランスが法人化するときの登記の注意点
フリーランスが法人化する場合、以下のような登記の注意点があります。
法人形態の選択
法人化する場合、どのような法人形態を選択するかが重要です。
代表的な法人形態としては、株式会社、有限会社、合同会社などがあります。
適切な法人形態を選択することで、企業活動を円滑に進め、リスク管理や経営戦略の立案などにも役立てることができます。
各法人形態にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、自社のビジネスモデルに合った法人形態を選択することが重要です。
登記簿謄本の取得
法人化する場合は、登記簿謄本の取得が必要です。
登記簿謄本は、法人の基本情報や役員名簿などが記載された重要な書類であり、法人設立や契約締結などの際に必要となります。
適切な登記簿謄本を取得することで、法人の正確な情報を提供し、信頼性の高いビジネスパートナーとして認められることができるでしょう。
資本金の設定
株式会社などの場合、資本金を設定する必要があります。
資本金は、株主の出資金額を表し、法人化する際には最低限必要な額が法律で定められています。
資本金は企業の信用力や安定性にも影響を与えるため、事業計画を考慮した上で適切な資本金の設定が必要です。
役員の任命と登記
法人化する場合は、役員を任命する必要があります。
役員の任命は経営陣を明確にし、業務の分担や責任の所在を明確にするために必要です。
役員の種類や人数は、法人形態や規模によって異なりますが、最低限代表取締役を任命する必要があります。
役員の任命に伴い、役員の住所・氏名などの情報を登記する必要があります。
法人名の登記
法人化する場合は、法人名を登記する必要があります。
これは、法人としての正式な名称を決定し、法的な手続きや契約などに必要となるためです。
また、登記することで法人名の使用が認められ、商標権や著作権の侵害を防止することができます。
さらに、既に使用されている法人名との重複を避けるために、登記前に法人名の検索を行うことが重要です。
税金の手続き
法人化する場合は、税金の手続きを行う必要があります。
法人税や消費税、源泉徴収税など、法人化に伴い変更が生じる税金があるため、税務署に法人設立届出書を提出し、法人としての税務登録を行います。
もし税務署からの税務調査が入った場合には、適切に対応する必要があります。
事前に税理士などの専門家の支援を受け、適切な対応を行うようにしましょう。
法人化しても案件紹介が可能なフリーランスエージェント
レバテックフリーランス|登録者数No.1

リンク先:https://freelance.levtech.jp/
「レバテックフリーランス」は、登録者数がNo.1なのに、利用者の平均年収が862万円という業界最大級の案件数を保有する完全無料のフリーランス専門エージェント。
週3日~働けるフルリモート案件も豊富です。もちろん、リモート案件には全国各地から応募できます。

参画にあたっての単価交渉や契約の手続き、福利厚生プランなども整えているフリーランスエンジニアに寄り添ったフリーランスエージェントです。
- レバテックフリーランスの仕組み
| 登録者平均年収 | 約862万円(当社調べ) |
|---|---|
| 案件数 | 41,247件(2022年11月) |
| 案件数(リモート・在宅) | 14,801件(2022年11月) |
| 案件数(副業・複業) | 4,593件(2022年11月) |
| 支払サイト | 月末締め翌月15日(15日サイト) |
| マージン | 10%〜20%(当社調べ) |
| 最大の特徴 | 登録者数No.1 |
- レバテックフリーランス独自のサービス一覧
- なぜレバテックフリーランスなら年収が上がるの?
- フリーランスじゃなくても登録できるの?
- 登録することで福利厚生がサポートします。
Midworks|週3日・リモート案件が豊富
「Midworks(ミッドワークス)」は、価格や案件などの総合的な評価が高い、IT系フリーランス専門エージェントサービス。
案件の掲載数は常に3,000件以上あり、業界最大手のレバテックフリーランスに匹敵する案件数です。
正社員並みの待遇で、フリーランス特有の急なリスクを事前に防ぐことができるのが特徴。
例えば、案件が急に途切れてしまった際の給与保障制度や、生命保険料の半額負担が福利厚生として整っています。
組織・団体に所属せず、雇用や収入が安定しないフリーランスにとって、税務保障制度や保険制度が充実しているMidworksは、かゆいところに手が届くサービスです。
| 登録者平均年収 | 約700万円(当社調べ) |
|---|---|
| 案件数 | 4,451件(2022年2月) |
| マージン | 25%〜30%(当社調べ) |
| 最大の特徴 | 正社員並みの手厚い保障 |
- 週3〜4日の案件多数
- 保険料負担額50%
- 会計ソフトfreee 利用料(無料)
☆仕事が途切れても60%を報酬保証!!
☆今の単価の2倍も夢じゃない!!
ITプロパートナーズ

リンク先:https://itpropartners.com/
「ITプロパートナーズ」は、週2日〜の副業案件に強みがあるフリーランスエージェントです。
IT業界で起業を目指す人でも利用できるので、一人起業でも安定して案件を獲得できます。

週2~3日からフルタイムまでさまざまな案件がそろっているので、起業までに一定の収入を確保したい人や余っている時間を活用して稼ぎたい人におすすめです。
| 最も高い単価 | 90万円 |
|---|---|
| 案件数 | 5,286件(2022年11月) |
| 案件数(副業) | 88件(2022年11月) |
| マージン | 非公開(当社調べ) |
| 最大の特徴 | 週2日から働ける副業案件が多い |
※ITプロパートナーズは週2日からの案件紹介が可能なものの、会社員をされている方の副業は紹介できません。
>> ITプロパートナーズの口コミを見る
- その他のエージェントの比較も見る
まとめ|フリーランスエンジニアの法人化は慎重に!
フリーランス(個人事業主)からの法人化は、法的な知識が必要となるため慎重になりましょう。
とくに納税や社会保険の加入については、フリーランスと大きく異なる点があるため、十分な下調べが必要です。
また、近年は法の改正による免税条件や控除額の変更、社会保障制度の見直しが行われ、制度の仕組みが複雑化しています。
現在の事業運営が思わしくない場合や、法人化してもメリットが少ないと予想される場合は、法人化を見送りましょう。
